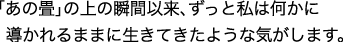
第4回 小菅正夫/旭山動物園園長
インタビュアー/石原嘉孝/オクノ社長
生き物に関する多くの知識を持ち、
土台をしっかり作っていなければ、
「生きているものとは何か」が見
えないんですよ。
石原:今西錦司さんの本で知りましたが、
19世紀以降、ヨーロッパの動物学は「反擬人主義」になり、
高等動物というのは擬人的なので、
学問対象からはずすようになったのだそうですね。
大学やアカデミズムでは、もっぱら小動物を研究対象とする。
高等動物をやるのはアマチュアだ、という変な風潮が生まれ、
それが日本の大学や研究機関でもそのまま受け継がれてきた、
と書いてありました。つまり、
アカデミズム「小菅動物学」は「牧田動物学」に、
まるで歯が立たなかった、というわけですね。
小菅:そうです。
そのアカデミズムの風潮に風穴を開けたのが
今西錦司さんです。
今西さんの霊長類の研究「サル学」は、
日本動物学が世界に向けて放った偉大な矢です。
サルやその他の高等動物は見て楽しむもので、
学問の対象ではないとしていた従来の生物学に対して、
今西「サル学」は革命を起こしたわけで、
それが京都大学の「霊長類研究所」に継がれて行きます。
今では、イギリスの研究者等はすっかり地の利を生かして、
旧植民地であるアフリカで盛んにチンパンジーやその他の動物を研究していますが、
それらは今西さんによって開かれた道ですよ。
石原:その意味では旭山動物園における牧田さんは、
今西錦司であったわけですね。
小菅:牧田さんがいなければ、僕も動物園づくりをするのに、どこかのマネをするしかなかったでしょうね。生き物に関する多くの知識を持ち、土台をしっかり作っていなければ、「生きているものとは何か」が見えないんですよ。生物の進化とか自然とかの知識も含めてね。
石原:園長や牧田さんの頭の中には「種の起源」をはじめ、
生物全体の構図が収まっているのですね。
小菅:生物の進化の系統図があって、
類・科・目に至る全体図と詳細図がありますよ。
自然環境分布図やその歴史的変化も含めた立体的な”地球史”が、
カラーで頭の中にあります。
でも、いまではもしかしたら「『系』
全体に意志がある」のでは
ないかという気がしてきました。
石原:ちょっと専門的な話になりますが、
「進化論」は、いまどんな感じですか?
小菅:「生物の進化」を考えた時、実際の動物をよく見てみると、
進化論では否定されている「要・不要説」の方が説明しやすい現象がずっとたくさんあります。
その生物にとって、利点のあるものは残され増強され、
不要なものは追い出されるということです。
その利点を、「進化論」では「個体の獲得形質」と捉えています。
でも僕は、それはある1匹、1頭といった『個体』ではなく、
「『種』全体の獲得形質」と考えるべきだと思ってきました。
つまり進化は「個の意志」ではなく「種の意志」であると。
でも生き物をよく見ていると、
いまではもしかしたら「『系』全体に意志がある」のではないかという気がしてきました。
石原:もう少しそこのところを…。
小菅:つまり『種』は単独では存在出来ません。
要するにその『種』の存在する環境=全ての生き物や無生物も含めた周りがあって、はじめてその『種』は存在しているわけです。
ですから、それらの関係する「『系』全体の意志」に導かれて『種』が生まれ、
変化して、今があるのではないか、と最近は考えるようになりました。
進化とは、だから「『種』の意志」ではなく「『系』の意志」にあるのだ、
と思うようになりました。
石原:ダーウィンの進化論に対して、
現代の先端研究や理論はどうなっているのでしょうか。
小菅:今では、反ダーウィンの嵐が吹き荒れています。
生物学者の中で一番注目されているのがやはり今西錦司だと思います。
私は「進化論」の専門家ではありませんが、
生物をいつも見ているとダーウィンの「適者生存」だけでは、
どうしても生物の進化を説明しきれませんね。
石原:今西錦司は、ダーウィンのいう「突然変異」つまり
「かたわもの」が育っていくわけないだろうって、
バサッと切り捨ててますよね。
小菅:今西錦司のスゴいのは、そういう攻撃的なことではなくて、
「生物というのは長い間見ていると、明らかになるべくしてなっている」というところですよ。
これは日本人には理解しやすいと思いますが、
西欧人にはスッとは解らないですよね。
でも彼等も生物をよく見ていくと、
今西理論に行き着かざるを得ないところまで来ました。
まぁ、進化論は10年、20年の観察ではどうにもならないことで、
結局は「哲学」です。
でも最近は「分子生物学」が出てきましたよね。
人間の遺伝子(DNA)の配列もすべて読み切りましたしね。
そんな中で、ウイルスが生物の細胞内に入り自己複製をするだけでなく、
その生物のDNAにウイルスのDNAが結合してしまうことがある。
そこで本体のDNAを変えてしまって新しい『種』が生まれる、
という理論が考えられるようにまでなっています。
これは「進化論」を「哲学」から「科学」に移すキッカケの一つです。
細胞内にあるミトコンドリアも他の生物から我々の細胞内に侵入した結果として、
酸素呼吸することが出来る「動物」が生まれたのではないか、
という理論なんかもそうです。
石原:「進化論」はそこまで来ていますか。
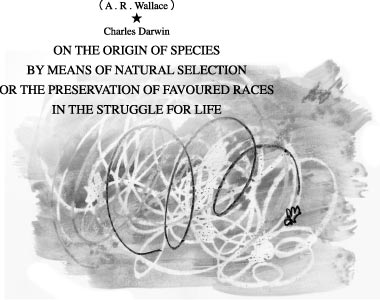
それが「どうも生物は神が創ったものじゃないよ」と
言ったのですから大変ですよ。
小菅:「突然変異」的偶然でそういう変化があったとしても、
その変化が、都合が良いかどうかというのも、
単にその生物だけの問題ではなくて、
他の生物や環境全体の都合に合っているものだけが生き残ってきた、
という考え方ですよね。
石原:その部分では、ダーウィンの「自然淘汰」論は、
まだ有効性を失っているわけではありませんね。
小菅:ただ「強者生存」、つまり強いから生き残る「弱肉強食」という言葉はかなり間違って用いられてきたと思います。
つまり、強い『種』が弱い『種』を食べ、結果として弱い『種』は滅びるというのは間違いで、一つの『種』の弱いものが他の『種』の強いものに食べられてしまう。しかしその『種』の強いものは生き残る。
そのようにして「各『種』においては強いものだけが生き残って来た」というように考えるべきです。
これが本当の「弱肉強食」であり「食物連鎖」の意味だと思います。
石原:なるほど、それの方が断然スッキリしますね。
小菅:そのような見方をすれば、
依然としてダーウィンの「弱肉強食=自然淘汰」論も正しいと言えますよね。
石原:ダーウィンの理論では、いささか機械論的ですものね。
小菅:そう。機械論的ですね…。勿論当時としては革命的な理論ではありましたが…。
石原:ヨーロッパではまだ強固だったキリスト教世界の真っ只中で、
「人間はサルから進化した」という理論を発表するために、
彼は『種の起源』を痛々しい程慎重に書き込んでいますよね。
小菅:それは恐かったでしょうね。
あの時代は「天地も生物も神がお造りになった」という考え方しか許されず、
生物の様々な『種』は神が創ったものだと言っている時に、
「いや、神は関係なく、『種』は自分自身で生まれ変化してきたのだ。」と言うわけですから。
それは全く反社会的な発言ですよね。
石原:ダーウィンの家系はイギリスのエリート階級です。
保守主義に囲まれていて一層慎重にならざるを得なかったんでしょう。
小菅:実は、ダーウィンの前に、
ウォーレスという人が同じく「自然淘汰」を考えて「進化論」の論文を書いていたんです。
『種の起源』が発表されたのは1859年ですが、
その前年にはその論文は書かれていて、
ダーウィンもそれを読んでいます。
結局、リンネ学会で1859年7月1日に二人同時に発表ということになったのです。
これには二人の社会的地位が関係しているかもしれませんね。
ウォーレスはきっと悔しかったと思いますよ。
石原:「進化論」は西欧では衝撃的な考え方として旋風を起こしたようですが、まぁしかし、そこに書いてあるものは、
日本人にとっては「それはそうでしょ。」というぐらいですよね?
小菅:それぞれの宗教観でしょうね。西欧では、
人間の上に絶対唯一神がいて、その神が人間を創り、
その他のものを創ったと信じているところに、
「どうも生物は神が創ったものではないよ」と言ったのですから大変ですよ。
我々のように多神教では、生物ばかりか石まで「意志」を持ち、神が宿っていると考えるのですから、「生物はみな同じ」なんてごく自然の考え方です。
石原:その意味で、「旭山動物園」は日本人でなければできるはずがないものと言えますね。
動物の慰霊碑があるのも日本だけです。
そんなことは考えられないことのようです。
小菅:欧米では、動物園のスタッフですら、
動物を見るとき、それは自然の一部分であるとしか見ていません。
人間以外の存在に意志があるとか感情があるとか、
そのようには見ていないですよ。
一番わかりやすい例ですが、うちの動物達にはそれぞれ名前がついています。
生年月日は当然のこと、すべての戸籍も完備されています。
オランウータンの“ジャック”と“リアン”間に“モモ”が生まれ、
その下に“モリト”が生まれた、というようにです。
欧米の動物園では絶対にこれはしません。
名前を付けるのは人間(human being)、〈人としての存在〉だけという絶対的思考があります。
動物に名前を付けることに対する奇異感、違和感はスゴいものですよ。
私達のように「擬人化」をしません。
石原:生物学でいう「反擬人主義」の問題はそういう根元的な思考の問題ですか。
「擬人化」なんて僕ら日本人には、
「鶴の恩返し」や「浦島太郎」等々いろんなところでへっちゃらですが、
欧米人にはとんでもないことなんですね。
小菅:その「擬人化」の意味も我々と全然違います。
彼らのいう擬人化は「チンパンジーに人のマネをさせる」ことですよ。
僕らの擬人化は「そんなことをすると、あそこのキリンが見てるよ」とか、
タヌキに、「ほら、ポンポコやってるよ」といった程度ですよね。
そんな風に育った日本人だから、生き物を見たとき、〈キリンとしての存在〉〈タヌキとしての存在〉をみんなスッと感じます。
欧米の動物園では、動物達を見せる時、
「これはアフリカのどこそこの、こういうものだ」という見せ方です。
僕らのように「キリンの“アンナ”」という見せ方ではないのです。
絶対に名前を付けないし、そういう「擬人化」は絶対にしないんですよ。
たぶん心理的にできないのでしょう。
やるとしたら、人間をマネさせて、
動物に服を着せるようなやり方ですよ。
石原:ショー番組でよくやってますね。
小菅:あれには僕は、本当に耐え切れない気持ちです。
彼らは<チンパンジーとしての尊厳>を全く無視しちゃってます。
彼らが名前を付ける場合、それは個体識別の単なる記号としてです。
僕らが見るとチンパンジーはみな顔も違えば性格も違いますのでそれぞれに名前を付けるのは当たり前なのですが。
石原:世界中の動物園はみんなそうですか?
小菅:私が実際に見たのはオーストラリア、
アメリカのシンシナティ、
シアトル、シカゴくらいですが、
どこも全く動物に名前を付けていませんでした。
動物の慰霊碑があるのも日本だけです。
そんなことは考えられないことのようです。
彼らには人間以外のものは全く単なる環境物であり、
人間と別の存在であるという考え方が徹底しています。
>>僕の子供の頃、お袋が生姜と醤油で煮てくれたクジラの肉や
ベーコンは、美味しくて忘れられない味ですよ。
|
 |
|
|
|
2008 summer |
|
|
copyright (c) 2008 by OKUNO all right reserved |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|