|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
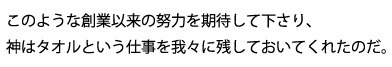 第7回 ホットマン創業者/田中富太郎 インタビュアー/石原嘉孝/オクノ社長 十数年前から全国のタオル産地はバタバタと潰れていきましてね。 今ではかろうじて泉州と今治がかろうじて残ったという状況です。 石原: その頃の日本のタオル主要産地はどこだったんでしょうか。 田中: 大阪の泉州が一番で今治と三重、これがタオル三大産地です。その他に愛知、静岡、九州でもやっておりました。技術では三重が一番高く有力な機屋がありましたよ。 石原: それらの多くの産地は、今はほとんど聞きませんが…。 田中: 近年の輸入品の急増で一挙に衰退してしまいました。 石原: 中国製が中心ですね。1995年頃より増えてきて2000年頃には輸入品が50%を超え、今では80%以上だと聞きましたが。 田中: そうなんです。十数年前から全国のタオル産地はバタバタと潰れていきましてね。今では泉州と今治がかろうじて残ったという状態です。 石原: タオル織機の登録割当で青梅は110台を確保しましたが、結局青梅はタオル産地にはならなかったのですか。 田中: いや、青梅でも一時ずいぶんタオル生産をやりました。でも、技術的な問題もさることながら感覚がねぇ…。 タオルをやっても、みんな「夜具地」の取引感覚の延長線上でやってましたからね。 1960年頃までは夜具地の産地として青梅は全国の圧倒的なシェアを持っていて、「日本の住まいに畳がある間は掛けふとんや敷きふとんの需要は減らない。 青梅夜具地は売れる」と言う産地神話がありました。でも生活文化がどんどん欧風化していきましたでしょ。60年代半ば頃にはその「夜具地離れ」が表面化して来て、 生産業者や買い継ぎ業者の倒産や廃業が相次いで、一気に衰退していってしまいました。 石原: 家庭にふとんが行き渡ってしまったからということではないのですか。 田中: そういうことではなく、やはり日本人のライフスタイルの変化によるものです。 ふとんでも青梅がやっていた従来の感覚の夜具地ではなく、見た目にきれいなプリント柄のものが出てきて、これに置き換わっていったからです。 その後、合繊綿が入った軽いふとんも出てきます。これらになると青梅のような小規模工場製品から大企業の製品に一挙に置き換わっていったんですよ。 石原: じゃ、ひとたまりもない状態ですね…。 田中: そうです。変化が出はじめたらあっという間にその波は広がっていって、既存の産地はもう手も足も出ません。 石原: 御社は夜具地だけでなくタオルや婦人服地なんかもやっておられましたから、まだ良かったですね。 田中: いえ、この産地での状況比較の問題ではありません。私の会社は小巾織物からすでに撤退済みでしたけれど、実は日本全体の産業構造の大変化が始まっていたのです。 その中で企業の継続がどうすれば可能かというギリギリの問題にウチ自身も直面していました。 でも正直なところ、 ずっと私は「タオル」というものにはほとんど期待もしていなかったんです。 親父の顔を立てるためのようなものでしたから…。(笑) 田中: そもそも私は「繊維の将来性はそんなにない」という感じを持っておりましたからね。何か新しいものをやっていかなければどうしようもないと真剣に考え続けていました。 石原: なるほど。 田中: ウチはずっと繊維の仕事です。繊維というのは何よりも感覚が大事で、重さや大きさや量といったことでは優劣はつきませんよね。絶対ということはありません。 石原: 色がちょっと違うだけで全然違いますね。 田中: 他の業界とは全然違います。ですから他の業界から繊維の業界に滅多に入って来られませんが、同様に繊維からも他の業界に変っていけないんですよ。 そんなことでその頃私は自分の会社の方向をどうすればよいのか本当に迷っておりました。 石原: はぁ。 田中: 弟に経営の勉強をすることを命じ、若手の技術者をつけてタオル工場の運営の一切を委せたのです。 「タオルといっても今まであるものではなく、オリジナルなものをやれ」 「ウチでやっている婦人服の技術や方法も取り入れながら工夫せよ」と言ってやらせました。 石原: 新しいタオルの開発のために弟さんに期待してですね。 田中: でも正直なところ、ずっと私は「タオル」というものにはほとんど期待もしていなかったんです。ただ親父の顔を立てるためのようなものでしたから…。(笑) 石原: 御社におけるタオルの歴史の当初はそういうものだったんですか…。 田中: まぁ当初はね…。1970年になって、タオル1本に絞ろうと決断したのですが、それまでの何年間かはアレやコレや悩み、試行錯誤の連続でした。 繊維以外の環境設備関連事業なんかに手を出してみたり、どうすればこの会社と事業が継続できるかを考えに考えていました。 力をそこに集結して、全力で取組めば何とか突破口があるはずだ。 田中: ウチの社でその頃一番大きく損を出していたのが実はタオル事業です。染色部門が一番良くて婦人服地部門も利益が出ていましたがその他の事業はすべて赤字で、トータルでは大赤字です。 石原: タオル事業が赤字だった…。 田中: いくつかの事業部のうち他の人に任せていたものは全部赤字でした。まぁ、中途半端な事業の多角化の失敗です。それは結局全部私の問題なのですが、ムダな設備投資もしてしまいましたし…。 石原: はあ。 田中: その大赤字がわかった時には本当に弱ったなぁ、と思いました。これはもうやりようがない。資金的にももうもたない。待ったなしの状況でしたからね。 石原: 服地部門は利益が出ていたのに、それをやめてしまったのは…? 田中: その部門の利益が出ているといってもね、全体はウンと悪く、大赤字です。 それと服地は製造の始めから販売まで全部を自分で見ていなければならないのです。他人に任せられないんですよ。 2度ばかり他人に任せたことがあったのですが、その都度後始末をするのに大変だったんですよ。 石原: はあ…。 田中: ともかく会社としてはトータルな赤字が大きいですから、問題事業部の整理を急いでやらなければならない状態でした。 そうしないと赤字がどんどん殖えて、事業を始める前に考えた「親父の財産に手をつけない」「親父の顔に泥を塗らない」どころか、家屋敷も危ないところまで追い詰められました。 もう本当に待ったなしの状態に追い込まれてしまいました。 そして、「ここまで来てしまったからにはすべてを放棄して廃業する」と決心しました。 石原: はあ。 田中: そう決めたんですがね。更に考え抜いているうちにふとヒラメキがありました。つまり「そうだ。タオルだけは最終製品だ」と考えたのです。 今までは我が社の製品はどれも販売を問屋や商社任せにしていた。 でもやりようによってはタオルは最初から最後まで自分達だけでできる。 経営力をそこに集結して、全力で取組めば何とか突破口があるはずだ…とね。 石原: はぁ…。 田中: そのように考え抜いた上で、「事業をタオル1本にして再出発する」と親父と弟に話しました。事業のいろんなトラブルや状況も説明しました。 そしてタオル一本に絞ることに決めた上、今まで製造の中心にいた弟やその技術屋は今後販売の仕事にまわること、「工場は俺が見る」ということにしました。 …そして再スタートしましたらね、タオル部門がすぐ黒字になったんですよ。 >>私は誰かの裏をかくというようなことは好きではありません。
|
|||||||||||||||||||
